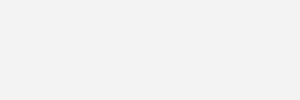コーヒー用品無限増殖バグ
デスクワーク中は、手慰みにずっと何かを飲み続けている。近年はUCCドリップポッドと台湾茶をローテーションしていたが、ここに来てそのルーティンが変わってきた。その過程で手元にやってきたコーヒー用品について書いていきたい。
background
元々コーヒー豆を手挽きしてドリップすることは嫌いではなかった。しかし仕事中に挽くのが面倒になったのと、安いミルで浅煎り豆を挽いたときに、粒子サイズが全く揃わずドリップで不都合を起こす(微粉が多すぎてフィルターに詰まってしまい、沼のような状態で抽出され、非常に苦く雑味に満ちたコーヒーが出てくる)という体験があったので、ここ数年来は手軽なポッドタイプのコーヒーメーカーに頼っていたのだ。
しかし中古で手に入れたデロンギの電動ミルが状況を変えた。手間無く一定品質の粉を挽けるようになり、それなりに適当なドリップでさえ、豆の違いを具体的に楽しめるようになったのだ。そして美味しいコーヒーは自分で淹れられると気づいた瞬間、さらなる体験を求めて道具を買い足してしまった。今日はその道具について記そうと思う。
basics
グッズを紹介する前に、ベーシックなセオリーについて記しておく。私はこの動画で基本的なドリップの手法を知った。James Hoffmann氏は2007年にワールドバリスタチャンピオンに輝いた人物だ。
ハリオV60というドリッパーのテクニックを紹介する動画だが、セオリーは他にも通用する。特に「浅煎り豆ほど高温で」という基本則は重要だ。これまでコーヒーのドリップといえば熱湯は避けるものだと思っていたが、そこからして間違いだったらしい。
goods
DeLonghi KG364J
まずはコーヒーミルだ。このモデルは全体的に大味な設計で不満もあるが、さりとて枷になるほどの欠点はない。腕が上がるまではこれで良いだろうと思っている。改造テクも出回っており、挽き目を弄ってエスプレッソ用の粉を挽くこともできるようだ。
Characteristics, Pros and Cons
- 粒子の均一性 (consistency)
悪くない。少なくともドリッパーに沼が生まれることはない。 - 粉残り (retention)
これは最悪で、10g入れたら4g吸い込まれることも珍しくない。挽いた粉をそのまま落とすのではなく、水平トンネルに押し込むという謎構造なので当然だ。 このため豆を量ってから挽くのは実用的でなく、挽いた粉を量る ことになる。なお分解せずとも後部をチョップしてやることで3g程度は回収できる。 - 掃除の難易度
分解は容易だが、掃除できる範囲はあまり多くない。しかもゴムリングや刃を正しくない向きにセットできてしまう。
誤ってゴムリングを刃の逆位置にセットすると、一見動くようだが粉を吐き出さなくなる。また刃を逆向きにセットすると、そのまま刃が外れなくなる。その場合の復帰手順はググれば出てくる。
Melitta アロマフィルター
初めに購入したドリッパー。基本的に放っておくだけなので、あまり手間を掛けずに抽出したいケースによくフィットする。
メリタ式では、コーヒー粉を入れたドリッパーに対して、規定量のお湯を一度に投入する。するとドリッパーの小さな一つ穴から、一定の時間を掛けてコーヒー溶液が抽出される。
Characteristics, Pros and Cons
どのドリッパーでも抽出時間によって風味が大きく変化するが、このメリタ式で抽出時間に影響するのは粉の挽き目くらいだ。本来豆の味を引き出すには、その豆や焙煎度に合わせた抽出時間の調整を求められるため、この方式は再現性に優れるが応用度が低い、という評価が一般的だ。おおよそその通りであると思う。
しかし初めの一歩としては良い製品だった。苦い酸いのギャンブルに陥ることなく、特に深煎りであれば美味しいものが飲める。が、浅煎りでこのドリッパーを活用するのは難しかった。挽き目や注湯によってフローレート(排出速度)を制御することも不可能ではないが、そもそも調整可能な要素が少ない。浅煎りを美味しく飲んでみたいという欲が出たので、他のドリッパーに移行することにした。
Kalita ウェーブシリーズ ガラスドリッパー 155
世の大半のドリッパーに刻まれているリブ(凹凸)を無くし、代わりにフィルターペーパーを波形に整形しているのが大きな特徴のドリッパー。
さらにフィルターの底がフラットになっており、これにより粉全体から均一に成分を抽出することができる......とされる。これは重要なことで、逆に部分的に粉が過抽出になったり抽出不足になったりすると、薄いのに苦くてエグくて酸いコーヒーになってしまう。
Characteristics, Pros and Cons
一発目から浅煎りを美味しく淹れられたのには感心したが、それにしてもデザインがこう......(オブラート)。赤色モデルはまだキッチュで良いかもしれない。
ORIGAMI air
ウェーブシリーズのペーパーが流用可能でありながら、デザインにも優れたドリッパー。このORIGAMIシリーズを用いてブルワーのワールドチャンピオンに輝いた人物も存在する。
Characteristics, Pros and Cons
ドリッパーの下部が大きくカットされており、さらにリブも深いため、フローレート(流下速度)が早い。このため注湯速度によって味は大きく変化する。と言っても思ったほど無理難題ではなかった。美味しい淹れ方はYouTubeにいくらでも上がっているし、むしろフローレートが早いぶん様々な動画のテクを再現しやすい。このORIGAMIが日々の主力ドリッパーとなった。
欠点もこの形状に由来していて、そのままグラスに置くと水平が取れず、しかし専用のトレイを付けたところで微妙に使い勝手が良くない。普段どおりドリッパーを掴んで持ち上げると、トレイだけがグラスの上に取り残されてしまう。まあ総合的にはデザインでおつりが来る。
加えてデジタルスケールとキッチンタイマーが一体化した、いわゆるコーヒースケールというものを安く買ってくることで良好な再現性が得られる。これで迷いもめくらめっぽうな判断も無くなる。
Clever
メリタと同じ浸漬式だが、より面白いアプローチを取っている。
まずこのドリッパー自体がメカ的で面白い。ドリッパーに注いだお湯はそのまま溜め込まれるが、グラスにドリッパーを載せた瞬間、音を立ててコーヒーが流れ落ちてくる。誰が見ても面白いギミックだ。
Characteristics, Pros and Cons
そして抽出結果は非常に印象的だ。雑味が少ないにも関わらず、しっかりと浅煎り豆の風味と甘みを含んだコーヒーを淹れることができる。強いて言うなら、結果次第で次回の抽出時に挽き目を調整するくらいでいい。
Clever独特のハックは「湯→粉の順に投入すること」だ。これによってより大きな豆の粒から先に沈め、微粉によるフィルターの目詰まりを減らし、コーヒーを素早く濾過することができる。高温と高速の2点が、浅煎り豆のドリップのキーポイントとなる。
同じアプローチを取ったものにハリオ社の "スイッチ" があるが、主な違いは淹れられるコーヒーの量とフィルターペーパーの形状だ。私はアロマフィルター1x2用の台形フィルターペーパーが大量に余っていたことから、ペーパーの流用が効くCleverのSサイズを購入した。
Bialetti Dama (2cup)
これまでのようなPour-Overドリッパーではない。いわゆるモカ・ポットとかモカエキスプレスとかマキネッタとか呼ばれるモノだ。
圧力を掛けて抽出することで、エスプレッソにやや近い濃いめのコーヒーを淹れることができる。最近ドリップで作ったカフェオレに物足りなさを感じ始めたので、ついにモカ・ポットに手を出すことにした。
Characteristics, Pros and Cons
DamaはMoka Expressがちょっと丸っこくなったバリエーションだ。これのせいでややネジを締め付けづらいが、そのデザインの秀逸さでおつりが来る。テクニックは例の如く James Hoffmann 氏の動画を参照して欲しい。
期待通りパンチの効いたコーヒーが得られる。これでカフェオレではなくカフェラテを作ることができるようになった。素晴らしい。
なお届いた製品は一体どこの倉庫に放置されていたものか、既にゴムガスケットが粉っぽく硬化しており、いくら締め付けても抽出中にボディの継ぎ目から水が漏れてきた。ガスケット変えたらすぐ直ったので、新品でもそういったケースがあるということを書き残しておく。